プログラミング教育の問題点【特別講座02】
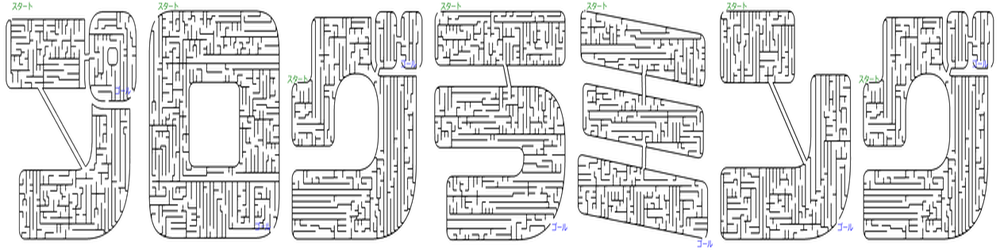
こんにちは。
特別講座プログラミング教育の第2回は「プログラミング教育の問題点」というテーマです。
この講座全体としては、プログラミング教育の理論(何を何故学ぶのか?)と実践(どう行動するか?)の両面から解説します。
想定する読者は「プログラミング教育に興味はあるけど知識が全然ない」という方です。
知識ゼロから読んでも、理屈がわかったうえで子供に具体的な教育を与える(教材を選定して学習を提案する)ところまで到達できるようにします。
本講座の内容
本講座 「 プログラミング教育の問題点」では、プログラミング教室や学校(小中高)で行われているプログラミング教育の問題点について解説します。
なぜ問題点について知る必要があるのかというと、既存の教育を無計画に受け入れてしまうと教育に失敗する可能性が高いからです。
教育に失敗する要因について知ることで、子供の教育環境の問題点にはやく気が付いたり、成功する確率が高い教育方法を選ぶことができるようになります。
プログラミング教育の3つの問題点とは?
さっそく、現在のプログラミング教育にある3つの具体的な問題点を説明します。
この3つは、どれも簡単には解決できない問題です。
この講座で、まずは問題の内容と原因について理解してください。
この後に続く講座(実践編)で、上手く問題を回避して子供の成長段階に合わせて最適なプログラミング教育をする方法をお伝えします。
それでは1つ1つ問題点を見ていきましょう。
問題点1:指導者のプログラミング能力がない
とにかく良い先生が足りません。
プログラミング教室の先生で高い技術力と指導力を持っている人はまずいません。
先生の年収は300万円〜600万円と高くない(優秀なプログラミング技術者の年収は1000万円~)ため、どうしても先生は人手不足になりがちです。
また小中高校の先生は、ほとんどプログラミングの経験がない状態です。多少の研修を受けたぐらいで教えられるほどプログラミング能力を習得することは簡単ではありません。
せいぜい、書店で1000円で売られている本に書いているような内容を読み聞かせることができる程度ではないでしょうか?
もちろん公教育としてクラス全員にプログラミング教育をすること自体に意味があります。
学校の授業として必修化すること自体は良いことなので、そこを否定する意図はありません。
ただ、学校で良いプログラミング教育を受けられる可能性は低いという話です。
良い指導者に教えてもらえる唯一の方法は、優秀なプログラミング技術者に個人指導を受けることです。
優秀なプログラミング技術者は観察力や想像力も高いので、教育者としても優秀なことが多いです。
ただし、 優秀なプログラミング技術者を見つけるには?見つけたとして相手が応じてくれるか?高額の指導料を支払えるか?などの問題があり、実現するのは難しいでしょう。
まとめ:良い先生がいない!
問題点2: プログラミングに成功した時の理想像がない
2つ目の問題点は、プログラミング教育が成功したらどうなるのか?というモデルケースが存在しないことです。
例えば野球選手であれば、成功モデルがあります。
甲子園で活躍・優勝→ドラフト1位でプロ→新人王&一軍で活躍→メジャーリーグ→指導者として成果
という具合です。
その結果どうなるかというと、子供が変な道に進んでしまい才能を活かせない可能性が出てきます。
プログラミング教育に成功した後の正しい姿がない、あるいは関係者に共有されてないため、ある程度上手くいった子供が進む道がバラバラになります。
ある子供はひたすら知識を増やすことに執着し、その才能や能力を社会に良い影響を与えるために使おうとしません。
別の子供はゲームにハマり、四六時中ネットゲームをやっていたりします。
あなたも子供のころ、「勉強して何の意味がある?」と思ったことはないでしょうか?
子供が教育を受けられる期間には限りがあります。一般的には3歳~22歳までの約20年間です。
もっと言えば、あなたが子供に教育できる期間にも限りがあります。一般的には3歳~13歳の約11年間です。
この貴重な時間を活かせないとしたら、あなたの子供にとって大変な損失になります。
ある意味、最大の問題といっても良いかもしれません。
なので、この問題点に関しては少しだけ解決策のヒントを紹介します。
あまりにも成功しすぎのためモデルとして適切かどうかわかりませんが、大学在学中に音声機能付き電子翻訳機を発明し特許の契約金として1億円を稼いだ孫正義(そん まさよし)の事例は、プログラミング教育の成功モデルといえるかもしれません。
プロ野球選手になって年俸3億円という世界があるのであれば、「プログラミング教育の成功とは大学を出るまでに1億円稼ぐことだ!」というような世界があってもいいかもしれませんね。
とにかく、プログラミング教育に成功したらこうなる!という具体的な理想像を持たないままに教育をしていることが問題です。
あなたなりの理想像をもって、子供のプログラミング教育を考えてください。
まとめ: 教育に成功した子供の姿をイメージできてない!
問題点3:生徒数が多くてサポートの手が回らない
3つめの問題点は先生ひとりに対して生徒が多すぎることです。
小中学校では、義務標準法で1クラスの生徒数は40人と決まっていて、それだと生徒が多すぎるので35人がいいとか、30人がいいとか言われています。
しかも、これは算数や国語といった普通の教科の話です。
幼児教育アカデミーの考えるプログラミング教育は、何かを覚えたり理解したりすることではありません。
何かを作りたい!という目標に向けて進んでいく中で発生する様々な問題に、試行錯誤で対処していく中で能力(あえて言葉にするなら、課題を発見する力と問題を解決する力)を磨いていくものです。
どちらかと言うと理論や座学ではなく、実践であり実学です。
それゆえに、発生する問題をサポートする先生の負担は大きくなります。
目安としては、ひとりの先生が同時に見られるのは優秀な先生でも10人まででしょう。
それ以上になると、生徒側に待ちが発生したり、問題を解決できずにモチベーションが低下にしたりという事態になってしまいます。
そうなると現実的には生徒を3~4人のグループにして、先生はグループ単位でサポートするしかなくなります。
その場合はグループ内で学習のフリーライダー(ただ乗り)が発生してしまい、学習効果が落ちるという別の問題が起きてしまいます。
このように、プログラミング教育には先生のサポートに限界があるので、あなたの子供が十分な教育を受けることは期待できないのが現状です。
まとめ:先生ひとり=生徒10人を超えるとサポートしきれない!
おわりに
本講座 「 プログラミング教育の問題点 」では、あなたが子供に良いプログラミング教育をするために解決する必要がある3つの問題点について解説しました。
忘れてしまった方のために再度まとめます。
3つの問題点のまとめ
- 良い先生がいない!
- 教育に成功した子供の姿をイメージできてない!
- 先生ひとり=生徒10人を超えるとサポートしきれない !
いかがでしたでしょうか?
きちんと内容を理解できていたでしょうか?
プログラミング教育をするにあたって、何を解決しなければいけないかという問題点をしっかり把握してないと、進むべき道が分かりません。
仮に「エイヤッ!」と何かを決断して進んだとしても、結果が良かったのか悪かったのかすら判断できない、という事態になりかねません。
そうなったら最後、色々な人に「~の塾がいいよ」とか、「~という勉強法がいいと」とか色々なことを言われて、勧められるままに色々なものをつまみ食いのように試すことになって、子供の最も貴重な財産である時間を食いつぶしてしまうことになるでしょう。
子供がしっかり成長して自分で判断できるようになるまでは、親がしっかりとした考えを持って子供の代わりに判断・決断する必要があります。
そのためにも、ぜひ本講座の内容を自分のものにしていただければと思います。
そして、次回以降の講座を最大限に活用してください。

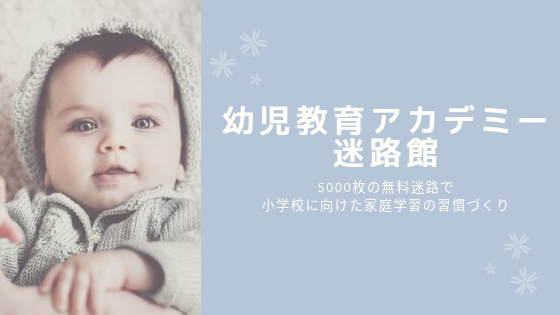


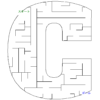
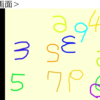
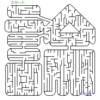


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません